因数分解は、中学数学から高校数学まで幅広く登場する重要な単元です。本記事では、基本の考え方から公式の使い方、つまずきやすい応用問題まで、段階的にわかりやすく解説します。
因数分解とは
因数分解の説明
「因数分解(いんすうぶんかい)」とは、ある式を「かけ算の形に直す」ことです。例えば、
という式を見てみましょう。
この式には「 \(x\) 」という共通の文字があるので、\(x\) でくくることができます。すると、
となります。
このように、もとの式を「かけ算の形」に変えることを「因数分解」といいます。また、このときの\(x\)や \(x+3\)のような、分解されたパーツが因数です。逆に、\(x(x+3)\) を\(x^2+3x\)に戻すことを「展開」と呼びます。
因数分解と展開の関係
「展開」と「因数分解」は、まさに逆の操作です。
展開は「かけ算を足し算の形に直す操作」、因数分解は「足し算をかけ算の形に直す操作」です。つまり、展開を理解していれば因数分解も理解しやすくなります。因数分解の問題の多くは展開公式を逆に使います。
因数分解と素因数分解の違い
よく混同されるのが「因数分解」と「素因数分解」です。名前は似ていますが、まったく異なる考え方です。
- 因数分解は、文字式の積の形で表す
- 素因数分解は、数を「素数(1と自分自身でしか割れない数)」の積の形で表す
因数分解の解き方
因数分解の方法はいくつかありますが、最初に覚えたいのは次の2ステップです。
順番に見ていきましょう。
.webp)
共通因数とは
式のすべての項に共通して含まれる数や文字を「共通因数」といいます。共通因数を見つけてくくることを「共通因数でくくる」といいます。
この式には「\(3x\)」が共通して含まれています。よって、 \(3x\)でくくると、
となります。まずは、どんな式でも「共通因数がないか?」を最初に確認するクセをつけましょう。
公式を使った因数分解の解き方
共通因数でくくったあとに使うのが「公式」です。よく使う4つの基本公式を覚えておきましょう。
因数分解の公式
これは【公式2】の、 \(a^2+2ab+b^2=(a+b)^2\)の形に似ています。 \(a=x\), \(b=3\)と考えると、
となります。
これは\(x^2-4^2\)と見ると、【公式4】のように、「(2乗)−(2乗)」の形になっているので、
と因数分解できます。
因数分解の間違えやすい問題
ここからは、実際に問題に挑戦していきましょう。
3つの文字が使われた一見すごく複雑な式ですが、実は綺麗な形に因数分解することができます。
先ほどの2ステップに沿って解いていきましょう。
.webp)
step1: 共通因数でくくる
この式を見渡してみると、 \((x^2+4y^2-z^2)^2\) と \(16x^2y^2\) に共通の因数はありません。
step2:公式を使う
では次の「step2:公式を使う」へ進みます。因数分解で使える公式は以下の4つでした。
\(16x^2y^2=(4xy)^2\) ですので、\((x^2+4y^2-z^2)^2\) と合わせて考えると、全体では「(2乗)−(2乗)」の形になっています。したがって、ここでは【公式4】を使うことができますね。それでは、早速この公式を使って問題を解いていきましょう。

ここまで整理できたら、今度はそれぞれの( )の中身に注目してみましょう。


ゆえに、最後に1つ目の( )と2つ目の( )を合体すると、解答となる
に辿りつきます。
高校数学で習う因数分解
因数分解で間違えやすい問題(高校数学)
高校範囲では、複雑な因数分解が出てきます。先ほどの「2ステップ」を応用すれば解けるため、ぜひチャレンジしてみてください。
一見ややこしく、共通因数でくくれるのか、公式が使えるのか分かりませんね。そこで、まずはどれか1文字に注目して整理してみましょう。ここでは\(a\)について整理してみます。

ここまで整理できたら、再度全体の式を見渡してみましょう。どの項にも\((b-c)\)があることに気付けるはずです。つまり、\((b-c)\)が共通因数ですね。ここからは、先ほどの2ステップに沿って解いていきます。
.webp)
step1にしたがって、全体から\((b-c)\)をくくりだしてみましょう。

いよいよラストスパートです。最後に残った\(a^2-a(c+b)+bc\)について、アプローチしていきます。ステップの順番に考えていきましょう。
step1:共通因数は既に\((b-c)\)でくくりだせています。
step2:ここで、【公式1】を使うことができます。
よって、\(a^2-a(c+b)+bc = (a-b)(a-c)\)となります。

よって、前にくくりだした\((b-c)\)と合わせて、最終的な答えとしては、\((a-b)(b-c)(a-c)\)となります。
たすき掛けを使った解き方(高校数学)
因数分解の公式にあてはまらないときは、「たすき掛け」という方法を使います。
たすき掛けは、\(acx^2+(ad+bc)x+bd\)の形の式を因数分解するときに使います。\(acx^2+(ad+bc)x+bd\)の式は、因数分解すると\((ax+b)(cx+d)\)の形になります。
以下の例題の場合、
- \(a, c\)はかけて\(3\)になる
- \(b, d\)はかけて\(-6\)になる
- \(ad+bc = -7\)になる
という数字\(a, b, c, d\)の組合せを見つける必要があります。
.webp)
この数字の組み合わせを見つけるために使えるのが「たすき掛け」という手法です。
それでは、たすき掛けの手順を見ていきましょう。
<たすき掛けの手順>
- かけて\(ac\)の数になる\(a\)と\(c\)の組み合わせを、縦に並べて書く
- かけて\(bd\)の数になる\(b\)と\(d\)の組み合わせを、縦に並べて書く
- 斜めに掛け算して、\((ad+bc)\)に合う数字の組み合わせを探す
- 正しい組み合わせを見つけたら、因数分解の形に書く

たすき掛けは例題を見るのが分かりやすいので、一緒に見ていきましょう。
このとき、
- \(ac\)について、掛けて3になるのは「1×3」「3×1」など
- \(bd\)について、掛けて-6になるのは「1×(-6)」「(-2)×3」など
があります。
これらのうち、たすき掛けをして\(ad+bc=-7\)になるのは、次の図のときです。

したがって、\(a=1, b=-3, c=3, d=2\)となるため、\((ax+b)(cx+d)\)の形に因数分解すると、
となります。
まとめ:因数分解のコツ
今回は因数分解の解き方について解説しました。
これが因数分解を解くポイントです。
複雑な問題を見ても、自分が知っているどれかの方法で必ず解ける、と信じて取り組みましょう。因数分解は、高校数学や入試問題の基礎でもある、非常に重要な内容です。最初は練習が必要ですが、パターンを覚えれば必ず得意分野になりますので、頑張っていきましょう!
atama+塾・atama+ オンライン塾では、AI教材「atama+」を使って、数学の力を効率的に身につけることができます。詳しい情報や無料体験をご希望の方は、以下のリンクからお問い合わせください。
{{Posts-CTA}}

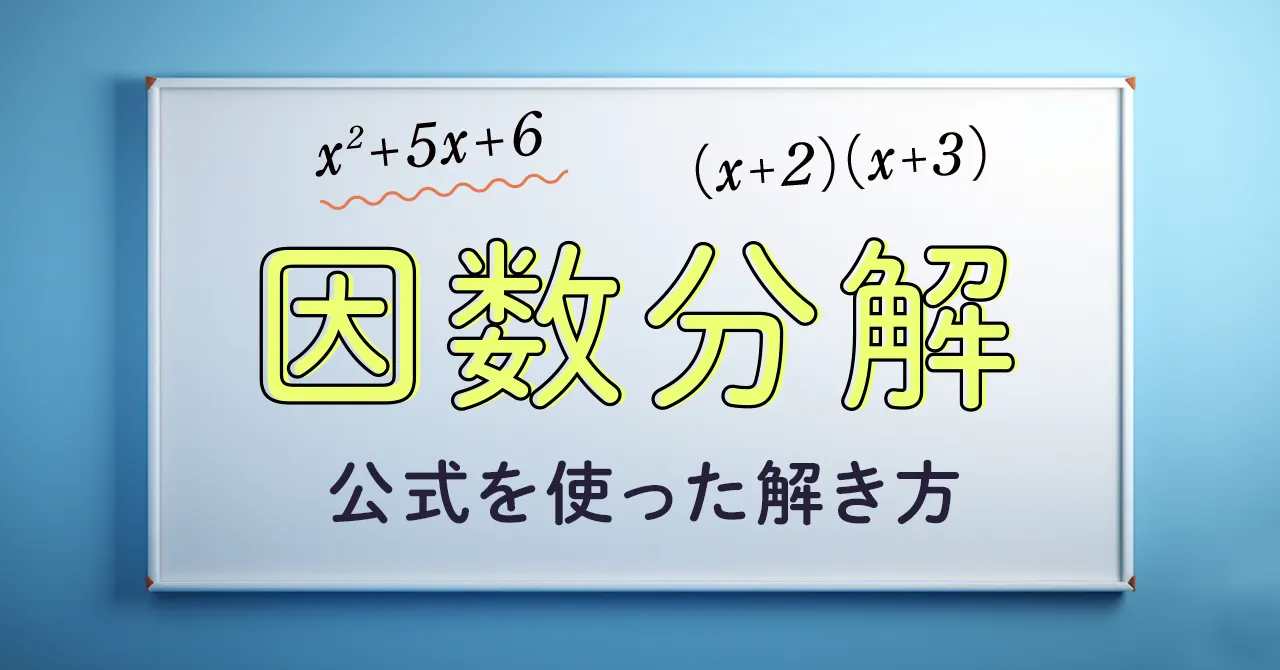
.svg)

.svg)